危険物取扱者とは?
危険物取扱者は、消防法で定められた「危険物」を取り扱うときに必要な国家資格です。
一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、タンクローリー等の施設には、危険物を取り扱うために必ず危険物取扱者を置かなければいけません。
どんな種類があるの?
まず「危険物」の種類ですが、6種類に分類されています。
| 第1類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物など |
| 第2類 | 可燃性固体 | 固体硫化りん、赤りん、硫黄など |
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウムなど |
| 第4類 | 引火性液体 | ガソリン、アルコール類、灯油など |
| 第5類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物など |
| 第6類 | 酸化性液体 | 過塩素酸、硝酸、ハロゲン間化合物など |
そして、資格は扱える範囲で3種類に分類されています。
甲種・・・全ての危険物において、取扱、点検・保安の監督、無資格者の立ち合いができます。難易度は最も高く、受験資格も必要となります。
乙種・・・第1類~第6類までそれぞれ別々の資格に分かれており、合格した分類の「危険物」において、取扱、点検・保全の監督、無資格者の立ち合いができます。
危険物の代表的なもので「乙4」と呼ばれるものは、乙種第4類のことで、ガソリンなど引火性液体を取り扱える資格です。
丙種・・・第4類のうち、ガソリンや灯油など特定の「危険物」のみ取扱い可能です。ただし、甲・乙種とは違い無資格者の立会い業務はできません。
比較的難易度は低く、物理や化学の専門的な知識は必要ありません。
受験資格は?
乙種及び丙種は受験資格が必要ありません。
甲種を受験するには一定の資格が必要です。大きく分けて5種類あります。
- 大学等において化学に関する学科等を修めて卒業した者
- 大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者
- 乙種危険物取扱者免状を有し、実務経験2年以上
- 特定の乙種危険物取扱者免状を4種類以上有する者
- 化学に関する学科または課程の修士・博士の学位を有する者
難易度・合格率は?
甲種は取り扱える危険物の範囲が広く、本格的な物理・化学の知識が問われるため、難易度が高く、合格率は例年30~40%程度です。
受験資格が必要であることから、受験者は一定以上の知識を持っている前提でこの合格率ですので、なかなかの難易度といえると思います。
乙種の合格率は、第4類のみ30%前後で、他は60~70%程度となっています。全体的に難易度はそれほど高くないと言えるでしょう。
甲種よりも物理・化学の難易度は下がりますが、取り扱う危険物の性質などに関する専門的な知識が問われます。
第4類の合格率が低いのは、受験者数が圧倒的に多いことが要因と思われます。
まずは「乙4」といった感じで、知識の乏しい受験者も多く、難易度が第4類だけ高いわけではありません。
他の類の乙種試験に合格している場合、「法令」と「物化」の試験が全て免除されます。出題されるのは「性消」の10問のみとなるので、負担が大きく軽減されるでしょう。
丙種の合格率は50%前後です。
出題内容も基礎的なので乙種や甲種に比べれば合格しやすいでしょう。
役に立つ?
取ればなんにでも役に立つというわけでは当然ありません。
実務系の資格ですので、デスクワークの方には恩恵は少ないでしょう。
化学工場の作業員やタンクローリーの運転手など実務で役立つ場面が多く、ガソリンスタンド、化学工場、石油メーカーなどでは必要となってきますが、難易度がそれほど高い資格ではない為、持っているだけで圧倒的に有利というほどではないようです。
資格が必要となる可能性がある仕事としては、タンクローリー・ガソリンスタンド・消防士・製油所・製造業・大学や研究所・医療業界など幅広いです。
注意点として、乙種の場合、その職場に対応した危険物の種類の確認が必要でしょう。
どんな試験内容なの?
甲種・乙種は五肢択一式、丙種は四肢択一式です。
試験時間はそれぞれ
甲種/2時間30分 乙種/2時間 丙種/1時間15分です。
合格基準はそれぞれの単元で60%以上の正解で合格となります。
出題範囲は以下となります。
| 甲種 | 危険物に関する法令 |
15問 |
| 物理学及び化学 | 10問 | |
| 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 20問 | |
| 乙種 | 危険物に関する法令 | 15問 |
| 物理学及び化学 | 10問 | |
| 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 10問 | |
| 丙種 | 危険物に関する法令 | 10問 |
| 燃焼及び消火に関する基礎知識 | 5問 | |
| 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 10問 |
どうやって勉強したらいいの?
独学での勉強も可能です。
特に「乙4」は受験者数も多く、書店に行けばテキストや過去問も多く取り扱っています。
試験内容としては法律関係と物理・化学の知識が問われます。
と言われると、苦手だと思う方が多いかと思いますが、そこまで高度な内容ではありませんので、効率よく対策を取れば、基礎知識がなくとも合格は可能かと思います。
ですが覚えることが少ないわけではありませんので、効率よくするため、通信教育などを利用するのも大いにありだと思います。
独学をする上での一つポイントをあげるとするならば、テキストや過去問をあれこれ浮気をしないことです。
書店に売られているテキストは、良し悪しはあれど、基本的にはすべての内容を網羅しているものです。
分かりやすいところを掻い摘んでとするより、ひとつのテキストを信じて一通りやり込む方が勉強の効率はよいです。
申し込む方法は?
受験地のセンターまたは支部から願書を入手できるほか、インターネットでの申し込みも可能です。
詳しい内容は一般財団法人 消防試験研究センターからご確認ください。
まとめ
- 消防法で定められた「危険物」を取り扱うときに必要な国家資格。
- 甲・乙・丙の3種類に分類。乙はさらに6種類に分かれている。
- 難易度はそれほど高くはないが、法律や物理・化学の知識が問われる為、一夜漬けで受かるほどは甘くない。
- 試験方法は、甲種・乙種は五肢択一式、丙種は四肢択一式。
- 実務系の仕事では役に立つ場面が多い。

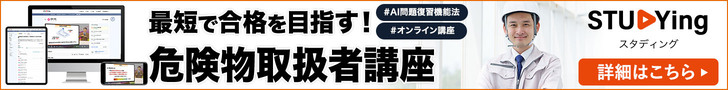


コメント